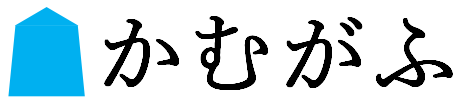Kamugafu
有段者の育成に注力する理由
先日発表した通り、「初段昇段~二段昇段(将棋会館道場基準)のノウハウ構築」をこれからの注力ポイントの1つにすることに決めました。それに伴い、2020年1月からの開講方針を見直しました。 今までも取り組んできた有段者の育成に、より注力することをなぜこのタイミングで改めて宣言したのか?今回はその理由について書きたいと思います。 —– まずはじめに、「初段昇段~二段昇段」の定義を明確にしておきます。「” […]
2020年1月以降の開講方針について
2018年1月に千葉県印西市で教室をスタートし約2年。これまで3桁を超える方にお申込、ご参加いただきました。さらにこの1年は幸運なことに、ねりまさんさん、教室対抗戦、倉敷王将戦、テーブルマークこども大会など大会で非常にいい結果が出ました。これも皆さまのご理解、ご支援があってこそだと思っております。この場をお借りして御礼申し上げます。 週末の教室に加えて、大会や道場などで子供達を見ていると、上達には […]
一局の重み(実践篇 対局後の振り返り)
一局をもっと大切に扱いましょう、という話の続きです。前回は、対局中に考えたことについて書きました。最終回の今回は、対局後の振り返りについて書きたいと思います。はじめに、自身の対局を振り返るためには、棋譜を残すことが前提です。まずは、棋譜取りを習慣化してほしいと思います。大会や道場に行った日に、1局でいいので記録することから始めましょう。上手く指せた将棋、負けて悔しかった将棋、課題が残った将棋、何で […]
一局の重み(実践篇 対局中の思考)
対局前の準備、対局中の思考、対局後の振り返りの質を高めて、一局をもっと大切に扱いましょう、という話の続きです。前回は、対局前の準備について書きました。今回は、対局中に考えたことについて書きたいと思います。知人と行っている研究会は指定局面戦で持時間は20分60秒。10月の指定局面は、角換わり腰掛け銀の最新形(私が後手番)でした。ここは先手の分岐点で、激しく攻める手(45桂など)と守りを充実させる手( […]
一局の重み(実践篇 対局前の準備)
前回のブログでは、対局前の準備、対局中の思考、対局後の振り返りの質を高めて、一局をもっと大切に扱いましょう、と言う話をしました。今回は実践篇として、私のプライベートの研究会の対局から、その具体例を書きたいと思います。この研究会は、アマ強豪の知人と計4人で毎月1回かれこれ1年以上やっており、この10月からルールが若干変わり指定局面戦になりました。そして、初回の指定局面は角換わり腰掛け銀の最新形で、私 […]