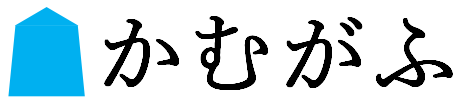夏休みが終わりました。満点には程遠いですが、教室として小中学生の全国大会、奨励会入会試験などで最低限の成果をあげることができたと考えています。
教室をさらに上に持っていきたく、身に付けていただきたい頭の使い方について書きます。学年は5,6年生以上、棋力は(この教室基準の)高段者向けです。
それは、「帰納」と「演繹」で、どちらも古代ギリシャから伝わる由緒正しい論理的思考法です。今回は、「帰納」について。
—
帰納的に考えるとは、複数の事象を集め、それらに共通する法則を見つけ出し、そこから一般的な結論を導き出す頭の使い方です。ビジネス、科学研究など幅広い分野で活用され、もちろん将棋にも使えます。
例えば
事象
・一昨日、太陽が東から昇って、西に沈んだ
・昨日も、太陽が東から昇って、西に沈んだ
・今日も、太陽が東から昇って、西に沈んだ
結論
太陽は東から昇り、西に沈む
これを将棋、昨日の夏の特別練習会に当てはめると、以下の話が挙げられます。
ある子の質問に対して、佐々木大地七段の回答を踏まえて私がこう話しました。
「駒の働きが悪くなる手はほとんどの場合、あまり良くない手だよ」
(イベント中は、その前に佐々木先生が「評価値」という言葉を使っていたので、私も合わせて「評価値を落とす(=あまり良くない手)」と言いました。)
これは、帰納的に考えて出した結論です。つまり、
事象
・Aという局面で、壁金を作った瞬間に攻められてしまって押し切られた。
・Bという局面で、角道を止めたので自分から攻めることが出来ず主導権を失った。
・Cという局面で、遊び駒があり戦力が足らずに攻めが続かなかった。
などの経験に基づき
結論
・駒の働きが悪くなる手は、ほとんどの場合あまり良くない手
を得ています。
帰納的な考え方=いくつかの事象を見て、何が言えるんだろう?と考える頭の使い方を身に付けると、こんないいことがあります。
・自分の勝ちパターン、負けパターンがわかります
・大会、研修会、奨励会の1日全体を通した改善点を抽出できます
・相手の将棋の特徴、思考のクセを捉えられます。
世の中では、「帰納」と「演繹」の頭の使い方は、後天的に習得可能とされています。興味がある方は、親子で調べてみてください。
次回は「演繹」について書きます。
頭の使い方(帰納的に考える)
- 2025年9月7日
- 思考行動習慣