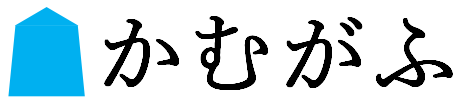頭の使い方シリーズ、前回は複数の事象を集め、それらに共通する法則やパターンを見つけ出し、そこから一般的な結論や仮説を導き出す「帰納」についてご紹介しました。
今回は、「演繹」について。
演繹的に考えるとは、一般的な結論や仮説から個別の結論や仮説を得る頭の使い方のことです。
例えば、
前回帰納的に考えて得た「太陽は東から昇り、西に沈む」という一般的な結論を使うと、
前提:太陽は東から昇り、西に沈む
事実:今、太陽が空に昇り始めた
結論:太陽が伸びり始めた方角は東だ
前提:太陽は東から昇り、西に沈む
事実:私の部屋の窓は西側にある
結論:私の部屋から夕陽が見える
が演繹的な頭の使い方の例です。
これを将棋に当てはめてみた例は以下の通りです。
前提:攻めの継続には、攻め駒は4枚必要
事象:私の得意戦法は角道を止める四間飛車だ
結論:私の身に付けるべき戦い方は、先攻ではなく反撃だ
演繹的な考え方=わかったこと(一般的な結論)から、具体的に何が言えるんだろう?と考える頭の使い方を身に付けると、こんないいことがあります。
・1つの物事を理解すると、合わせて複数の物事を理解できます=1局の学びを10局分の学びに膨らますことができます
・自分に関係が薄い話だったとしても、自分に置き換えて学ぶことができます=将棋に限らず、どんなことを学んでも自身の将棋に活かせます。
世の中では、「帰納」と「演繹」の頭の使い方は、後天的に習得可能とされています。興味がある方は、親子で調べてみてください。
次回は、「帰納」と「演繹」を身に付けるとどんなことが起こるのか、私の経験を踏まえて書きます。